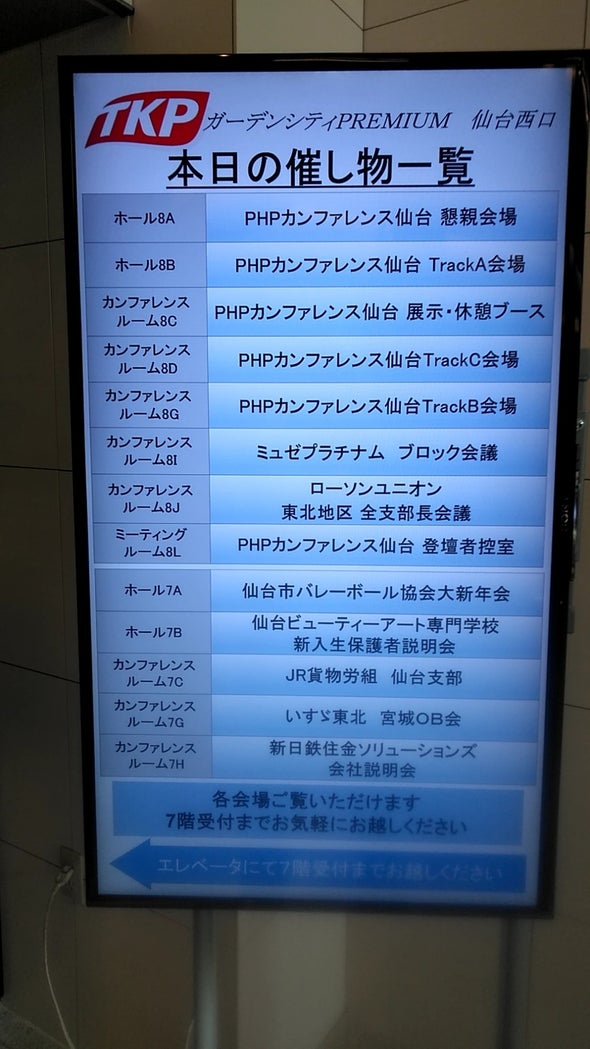Polymer.co-edo meetup #23を開催しました
Wednesday, March 27, 2019 12:51:00 PM
2019年2回目となる Polymer.co-edo ミートアップ を開催しました。
今回、私はいよいよEdoエレメントの作成に入りました。
名前は edo-blogcard です(まだリポジトリをPUSHしてないので、upしたら別の記事にします)。
これは、はてな等でブログにリンク先のサムネ、タイトル、概要の部品が入っているのを見たことがあると思うのですが、あれです。
これを LitLoader を使って作り始めました。
次回
2019年のGWに Polymer.co-edo day として開催予定を公開しています。
私が1日 co-edo で作業しているので、一緒にもくもくしたり、Web Components関連の質問を受け付けたり、
好きな時間に来て、帰ってもらっても大丈夫な1日になります。
皆様の参加をお待ちしております。